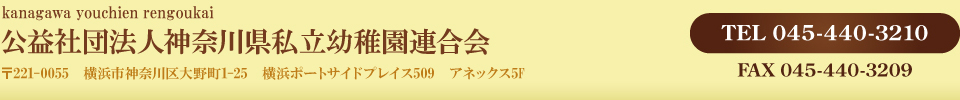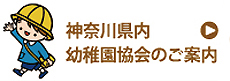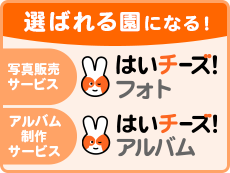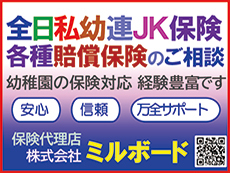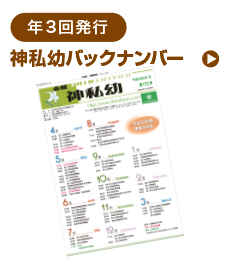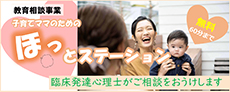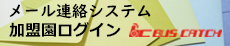免許状更新講習一覧
| 最終更新日:2022年3月1日 TOPIC:令和4年度免許状更新講習の開催予定はありません。 |
| *〜*〜*お願い*〜*〜* 教員免許は免許を所持するご本人様の管理となります。修了期限等、一人ひとり違いますので、当連合会では確認ができません。 免許更新制についての情報は文部科学省や神奈川県教育委員会のホームページでご確認ください。 (全国の免許状更新講習開催情報は、文部科学省のホームページ「教員免許更新制」をご確認ください。) |
| キャンセル専用メールは こちら |
※現在、免許状更新講習の受付はおこなっておりません。 このリンクは、キャンセル専用のメールアドレスリンクです。 キャンセルの方は、左の文字をクリック キャンセルメールには以下の内容を記入してください。 ●申込者氏名(ふりがな) ●生年月日 ●キャンセルしたい講習の講習コード (例)【原03】【県01】 ●受講料振込み済みの場合返金を受ける金融機関・口座番号をお知らせください。 キャンセルする講習の開催日の1週間前(同一曜日の24時まで)までにメールで連絡があれば返金いたします。これ以降の連絡は、理由の如何によらず返金は行いません。返金は各講習ごと(※)に事務手数料200円と、振込み手数料を引いた金額となりますのでご了承ください。 (※必修・選択必修は2講座となります) |
-
 ※現在、講習受付は行っておりません。
※現在、講習受付は行っておりません。